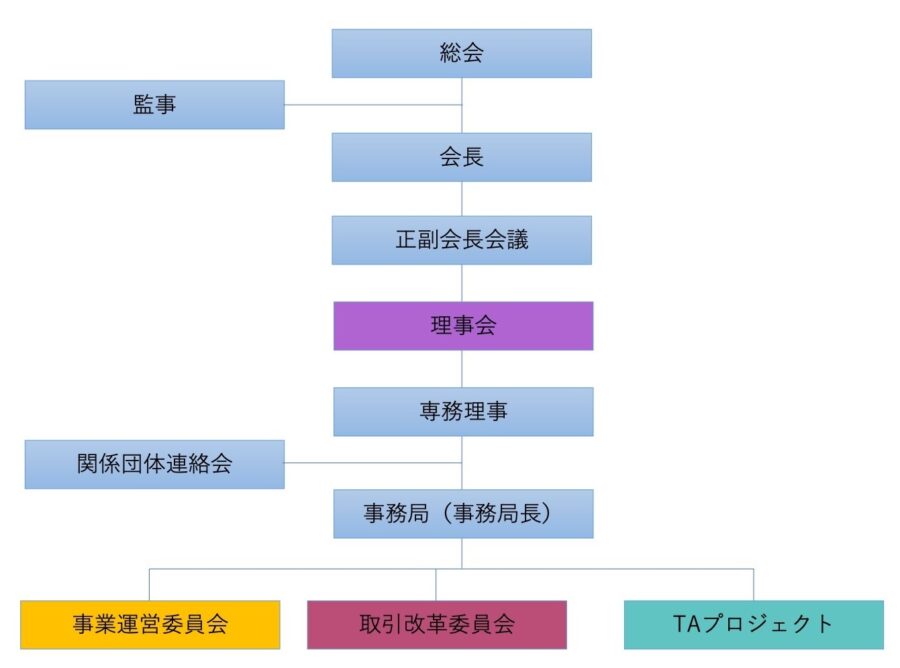Ⅰ.令和5年度事業報告
令和5年度の事業活動は、引き続き経済産業省ならびに各業界団体と連携を取りながら、「取引ガイドライン第三版」(以下 「ガイドライン」とする)と「自主行動計画」の普及啓発活動を推し進め、「適正取引」や「付加価値向上」につながる望ましい取引慣行を普及・定着させるための適正取引の推進と、サプライチェーン全体の取引適正化に向け活動した。
今回で18回目となる「聴き取り調査」は、6月から11月にかけて産地を含め計85社に対して行った。また、「自主行動計画」は第6版となる改定を行うと共に、「徹底プラン」を策定。11月には7回目のフォローアップ調査を行い、更なる周知・啓蒙に取り組んだ。
今後も繊維ファッション産業界の全体最適を目指したSCM構築を図るために注力していく。
Ⅱ.事業活動
1.「取引の適正化」事業
「取引の適正化」事業では、業界全体がコロナ禍からの回復途上にある中、例年通り適正取引に関する「聴き取り調査」をTAプロジェクト参加企業及び関連団体傘下企業に対し実施した。今回の調査では①「ガイドライン」の実践・進捗状況、具体的には「(売買)基本契約書」の締結状況、「発注書」の発行・入手状況、「歩引き」取引の実態、決済方法・手段の状況②「自主行動計画」の実施状況と価格転嫁の実態③CSR・サステナビリティの推進状況④サプライチェーンに対する社会的責任の推進状況、関連団体傘下企業を中心に⑤「外国人労働者」についてのヒアリング⑥パートナーシップ構築宣言と知的財産実施状況 の各項目について実施した。
また、平成26年から実施している産地を対象とした関連団体傘下企業「聴き取り調査」も本年で10回目となり、「聴き取り調査」は33社に実施した。
以下は調査結果概要である。
(1)「聴き取り調査」の実施
1)調査実施時期:令和5年6月~11月
2)調査内容
① 「ガイドライン」の実践・進捗状況
② 「自主行動計画」の実施状況と価格転嫁の実態
③ CSR・サステナビリティの推進状況
④ サプライチェーンに対する社会的責任の推進状況
⑤ 「外国人労働者」についてのヒアリング
⑥ パートナーシップ構築宣言と知的財産実施状況
3)調査対象企業:
TAプロジェクト参加企業(52社)及び関連団体傘下企業(33社)計85社
(業種区分については主体事業形態で区分)
| 業種 | 企業数 | 業種 | 企業数 |
| TAプロジェクト参加企業 | 52 | 関連団体傘下企業 | 33 |
| アパレル | 14 | テキスタイルメーカー | 3 |
| 商社 | 15 | ニット製品メーカー | 5 |
| テキスタイルメーカー | 8 | 織物企業 | 19 |
| 副資材メーカー・卸商 | 7 | 縫製企業 | 6 |
| ニット製品メーカー | 1 | ||
| 染色加工業 | 3 | ||
| 小売業 | 4 |
*ユニフォーム関連企業数13社はTAプロジェクト参加企業の業種ごとに加えられている。
*関連団体傘下企業33社の内、昨年度も調査した企業数は16社
(2)調査結果要旨
- 「覚書」を含む「基本契約書」は販売先・仕入先と概ね締結している。新規取引先との締結は義務付けているが、スポット、少額取引、古くからの取引先とは締結していないケースが多く、自社に不利な契約は敢えて締結しない企業も見られる。
- 「発注書」は販売先・仕入先とも概ね入手・発行している。「発注書」を受注の条件とする企業が多い。但し副資材メーカー・卸商はブランドホルダーの間接発注も多く、「指示書」での代用や「発注書」や「基本契約書」の締結に応じない先もあるため、在庫引き取り等に苦心する企業も一部見られた。
- 「歩引き」取引は各企業の長年に渡る交渉の結果、減少傾向にはあるが商慣習として根強く残っている。副資材メーカー・卸商はアパレル、縫製メーカーから、ユニフォームアパレルは代理店からの「歩引き」で、商社はスルー取引や物流費を負担する場合に多く見られる。
- 「決済方法・手段」について、販売先は現金58%(57%)期日指定現金14%(14%)手形13%(15%)電子債権14%(13%)で現金、電子債権が微増、手形・電子債権のサイトは90日以内60%(60%)で昨年度から変化は見られなかった。仕入先に対しては現金55%(52%)期日指定現金12%(15%)手形12%(12%)電子債権20%(20%)、手形・電子債権サイトは60日以内25%(23%)、90日以内48%(48%)、90日超27%(29%)で現金化とサイト短縮がやや進んだ。下請法適用仕入先に対しては現金70%(73%)期日指定現金2%(1%)手形13%(11%)電子債権14%(15%)、手形・電子債権サイトは60日以内36%(36%)、90日以内64%(64%)で現金・電子債権化は進まず、手形・電子債権サイトに変化は見られなかった。アパレル、商社の支払いサイトが比較的長く、改善されていない。海外生産比率が高く、資金回収までの期間が長いことや、コロナ禍からの回復が未だその途上にあることが影響していると思われる。
- 「基本契約書」の締結率は低く、回答をいただいた企業数の平均は販売先48%(42%),仕入先78%(76%)である。「発注書」について販売先からの入手率は84%(78%)、仕入先への発行率は78%(76%)。和装関係の織物企業「古くからの取引で信頼関係に基づいて商売をしている」、「発注書は作成する手間も考慮し入手、発行しない」との声も聞かれた。ウール関係織物企業からは「見積書と並行して発注書のフォームを販売先に送っても返ってこない」「生産開始後に値切り交渉される」とのコメントがあった。
- 「歩引き取引」は解消努力を継続して実施しているが、毛織物テキスタイルメーカーの一部と特に和装織物企業で和装・呉服問屋に端を発する「歩引き」が構造的に定着している。「交渉し続けているが法的規制をかけない限りなくならない」「交渉するだけムダ」とのコメントがあった。ほとんどの企業は単価に乗せることで対応している。
- 「決済方法・手段」について、販売先は現金73%(69%)期日指定現金7%(7%)手形9%(14%)電子債権10%(8%)、手形・電子債権サイトは60日以内23%(20%)90日以内39%(35%)120日以内13%(22%)210日以内26%(23%)である。現金化は進捗しているが、手形・電子債権サイトは織物企業、テキスタイルメーカーで長く、とりわけ和装関連織物企業は120日以上の比率が高く、210日も珍しくない。原料を仕入れ、製織、整理加工後に販売する企業もあり、資金回収までに相当な期間を要している。コロナ禍の対応では和装業界全体で事業を守る意識が強く見られるが、和装需要の回復は鈍いため、業界体質の改善が必要である。仕入先に対し、現金比率は80%(79%)と高く、手形・電子債権サイトは90日以内が70%(39%)であるが、やはり和装関係織物と海外縫製を行っている企業で120日以上のサイトが見られる。
令和 3年3月に「下請代金の支払い手段に関する通達」が見直され、下請代金に係る手形等のサイトについては60日以内とすること、そして、概ね3年以内を目途として可能な限り速やかに実施すること、となっている。「自主行動計画第6版」では下請法適用取引に係わらず、仕入先に対する支払いサイトは60日以内を目標とする旨が追加された。また、政府は「約束手形の利用廃止を2026年までに行う」との方針を掲げており、現状1割強ある手形決済の比率について「歩引き」と合わせて注視していきたい。
| 販売先に対し | 仕入れ先に対し | |||||
| 労務費 | 原材料価格 | エネルギー価格 | 労務費 | 原材料価格 | エネルギー価格 | |
| 概ねできた | 9 (7) | 9 (7) | 10 (8) | 29 (24) | 33 (26) | 31 (25) |
| 一部できた | 27 (20) | 36 (32) | 29 (24) | 17 (17) | 17 (23) | 17 (20) |
| あまりできなかった | 8 (15) | 2 (7) | 6 (12) | 2 (8) | 1 (3) | 3 (6) |
| 影響を受けない | 3 (5) | 0 (1) | 2 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (1) |
| 計 | 47 (47) | 47 (47) | 47 (47) | 51 (52) | 51 (52) | 51 (52) |
単位:企業数
| 販売先に対し | 仕入れ先に対し | |||||
| 労務費 | 原材料価格 | エネルギー価格 | 労務費 | 原材料価格 | エネルギー価格 | |
| 概ねできた | 12 (8) | 17 (12) | 13 (6) | 24 (21) | 30 (23) | 29 (21) |
| 一部できた | 16 (11) | 13 (12) | 16 (13) | 4 (4) | 1 (5) | 1 (6) |
| あまりできなかった | 4 (9) | 2 (5) | 4 (9) | 2 (4) | 0 (1) | 0 (2) |
| 影響を受けない | 1 (1) | 1 (0) | 0 (1) | 2 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
| 計 | 33 (29) | 33 (29) | 33 (29) | 32 (29) | 32 (29) | 32 (29) |
単位:企業数
2. 新規事業
令和4年12月に始まった「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」は、全16回の議論を重ね、令和5年11月30日に関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に最終報告書が提出された。最終報告書では、「新制度及び特定技能制度の位置付けと関係性等」、「新制度の受け入れ対象分野や人材育成機能の在り方」等、10項目にわたる提言を行い、現行の技能実習制度を廃止し、新制度を創設する方向性が示された。
繊維産業については現行制度では技能実習制度のみで特定技能制度が認められていないため、人材不足に悩む多くの繊維産業の中小規模事業者から特定技能への分野追加を求める声は多く聞かれていた。
当協議会では経済産業省からの働きかけもあり、繊維業界の特定技能の分野追加が認められることを見据え、特定技能制度の運営に携わることを当協議会の新たな役割として令和5年度の新規事業として位置づけた。
しかしながら、新制度創設の議論が進行中で具体的な制度設計は示されず、さらには新制度の具体的な運用方法についても情報が開示されることはなかった。そのような不確定な状態の中、当協議会が担うべき役割についても明らかにすることが出来ず、具体的な行動に結びつけることは出来なかった。
Ⅲ.委員会活動
1.事業運営委員会活動
事業運営委員会では協議会の運営強化や令和5年度事業報告、及び令和6年度事業計画の確認を予定。また広報活動を実施した。
今回の委員会では、令和5年度の「聴き取り調査」の結果方向や、「自主行動計画」のフォローアップ調査のフィードバック。また、技能実習制度の見直しや特定技能の分野追加等について意見交換を行う。
(1)「事業運営委員会」開催
第1回:令和6年3月5日(火)
(2)広報活動の実施
「FISPAニュース」の配信を実施。協議会の活動内容及び業界関連記事等について会員への広報活動を行った。
(3)事例研究セミナー開催
開催日時:令和6年3月8日(金)14:00~16:00
開催場所:TFTビル9階 909号研修室
演題:第1部「欧州繊維戦略」の概要と今後の課題
講師:株式会社東レ経営研究所 繊維・市場調査部主任研究員 安楽 貴代美氏
演題:第2部実践イノベーションの仕掛け学 ~過去から学び未来を創る~
講師:京都大学経営管理大学院 客員教授
前オムロン株式会社 イノベーション推進本部シニアアドバイザー 竹林 一氏
2.取引改革委員会活動
繊維ファッション産業界の各段階間の取引上に生じている課題について調査するとともに、具体的な解決策について検討を行った。諸官庁及び業界団体の情報交換と連携強化に努め取引の適正化を進めてきた。
今回の委員会では、令和5年度の「聴き取り調査」の結果報告や「自主行動計画」のフォローアップ調査結果のフィードバック。また、技能実習制度の見直しや特定技能の分野追加等について意見交換を行う。
(1)「取引改革委員会」開催:
第1回:令和6年3月7日
(2)「ガイドライン」普及啓発活動及び適正取引推進活動の実施
1)産地における聴き取り調査
業界全体における取引上の不公平・不公正な取引慣行の改善及び課題解決に向けた取り組みの推進を行うべく、産地における聴き取り調査を実施した。
2)自主行動計画フォローアップアンケート
昨年に引き続き、関連団体傘下会員に対し自主行動計画の実践状況についてアンケート調査を実施した。
(3)業界団体間での情報交換
各団体が抱える課題・問題点等、現況についての報告と価格転嫁の実態や技能実習制度の見直し、特定技能の分野追加等について意見・情報交換を行う。